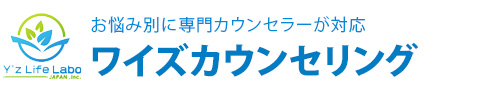Recently updated on 4月 27th, 2024
大阪・梅田ワイズカウンセリング 専門カウンセラー、公認心理師の石田 美咲紀です。
外出できず、外との交流を持てないお子様を抱えるご家族の方。
ずっと家にひきこもっている子どもを見て、辛い気持ち、イライラ、自分に何ができるか思い悩んでいらっしゃると思います。
我が子がいつ重い腰を上げて動き出すのかと居ても立っても居られない不安な気持ちになるのではないでしょうか。
毎日の生活で不登校になった我が子を見ると不安な気持ちに支配されて余裕がなくなって、ついきついことを言ってしまうあるいは言いそうになる葛藤も大きいと思います。
・学校に戻って勉強してほしい気持ち
・無理やりに引っ張り出してはいけない気持ち
・でもいつまでこのままの生活を続ける気なのか
結局、子どもの気持ちがわからない!となることもありますね。
個人と親の立場で矛盾する気持ちの仕組み
親として
・見守りたい気持ち
・いつ学校に復帰してくれるのか気になって仕方ない気持ち
を持つと思います。
どちらも真剣にお子様の事を考えて、よりよくなってほしいと思う気持ちがあるからこそ湧いてくる感情です。
愛情深くお子様のことを日々考えられている証拠であると思います。
苦しいときは自分を保つためについ、自身の行動や発言の軸が「自分が大変だから、苦しいから」となってしまいます。
そうするとついお子様にストレスをぶつけたり、子どものためではなく自分のための発言や行動になりやすいです。
今一度、愛情深く接していけるようなヒントやコツを紹介しますね。
家族のストレスがたまってしまうことへの対策についても一緒に考えていきましょう。
周りと比較する・思い込みやすい自分を認める
どうしてうちの子が..と子育て方針が間違っているのではないかと感じる
不登校の子どもがいるという悪い目で親族から見られる
世間や周りから出来が悪い子、問題児、家庭環境や親に責任があるというレッテルを貼られてしまっている
確かに実際に言われることもあるかもしれませんが、ご自身でそう思い込んでしまっていることもあるかもしれません。
初めての気持ちや状況でそれがネガティブなものだったら誰でも弱気になったり落ち込んで通常の状態ではなくなります。
弱っているときは根拠なく悪く思い込みやすいという癖を理解して下さい。
まず、苦しい状況でご家族が少しでも冷静になることが大切です。
これがストレスを減らし、嫌な考えやきつく当たってしまう可能性を減らせます。
お子様に対する姿勢を自動的に変えるコツ
ストレスや苛立ちは出していないつもりでも感じ取ることはありませんか。
例えば、職場、友人関係でも経験はないでしょうか。
家庭でも同じです。
まず、 その空気感を出さないようにしていきたいですね。
教育心理学の理論の一つに「ピグマリオン効果」という、教師の思い込みが生徒の成績を左右するという実験があります。
教師が生徒に「ダメな子」とみなすとそのクラスの生徒は点数が低く、「できる子」とみなすと成績が上がることが判明しました。
これは子育て、不登校のお子様にも当てはめて考える事ができます。
まず、お子様を「この子は少し休みたい時期、きっと大丈夫!」とみなすことを言い聞かせて下さい。
精神論ですが、教育心理学でも実証されていることですからまずは考えずに従ってみて下さい。
実際に、こういうふうに態度を変えて、毎日の中での小さな変化を見つけて下さい。
家事を手伝ってくれる、前よりも夜ふかししない、早起きできる。
少しでもできたら評価していけば自然と前向きな発言が増えていき、ご家族もそういう気持ちが出て、よりゆとりを持ってお子様に接することができます。
怪我をしたときのリハビリと同じ
この接し方を繰り返すと、本当にお子様は動き出す役割を自然にとるようになります。
さらに、お子様が少し休んで徐々に動き出すエネルギーを与える影響力につながります。
怪我のときのリハビリと同じで、急に動けなくても徐々にできればいいですね。
子どもにとって影響力の大きい親、学校の先生から“できる子”とみなす肯定的な目を向けることで本当に子どもはその役割を果たそうと無意識に動いていきます。
ぜひ先生にもこのブログを読んで頂き、意識してもらって下さい。
お子さんに対する「うちの子はダメ」という想いをまずご家族が取り払って、「大丈夫、やるときはやる子」と心から信じてみませんか?
子どもは心に愛情やゆとりエネルギーを蓄える必要があり、勉強や運動を活発に行うにはまず信頼される大人から信じてもらうエネルギーが必要です。
親も自分を褒めることでゆとりができます
同様にお母様、お父様もご自身を「自分はよくやっている」と親役割を肯定して下さい。
お仕事、家事で自分のことだけでも大変なのに、そうした中で今まで経験したことがないストレス状況下にいるわけです。
親として不安な気持ちを持ちながらも、自分を少しでも褒め称えることで家族全体が肯定的になっていきます。
引きこもり期間を学校ではできない教育と考えましょう
勉強だけが教育ではありません。
学校ではなく、家だからこそできることを少しずつやっていけば前進です。
家事、料理、掃除など普段お子さまが親に任せっきりだったことをしてもらえたら、それも学びです。
今のピンチのような状況をチャンスとまで考えられなくても、この現実からできることを意識していけるといいですね。
声掛けも必要ですが、お子様を見る目を少しポジティブに変えるだけでも影響力があります。
声掛けの仕方で悩み込んでしまう前に、少し見方を明るく変えてみるのも有効です。
まず、「こんな相談でいいのかな?」と迷う場合、LINEでお問い合わせだけでもいただければ直接カウンセラーがお答えします。
こんな相談でもいいのかなど気になることは、LINE宛に気軽にお知らせください。
カウンセラ ーが直接お答えします。
LINE登録をすると周りに相談することや医療機関の受診とカウンセリングの違いなどについて配信をご覧いただけます。
ぜひご登録下さい。
お問い合わせ
不安なこと、わからないことはLINEからお気軽にご相談ください。(お電話では受付していません。)
内容を拝見し、それぞれの担当カウンセラーが応答させて頂きます。
また、ご登録でお得な情報入手、カウンセリングを受けるメリットなども解説しています。

ID: @qpw6488w
営業時間:9:00〜21:00
最終受付(お問合せは24時間可能です)

専門:不登校児童、家族のメンタルケア・家族関係修復
学内ケース、学外実習、放課後デイサービスのアルバイト、家庭教師などを経験し、子どもたちの側で、そして、親御さんとも連携し不登校を解決してきました。
育った世代が近いからこそ、お子様と打ち解けてお話をして、最良な方法を提案しますね。